「関東 新春集会 2013」
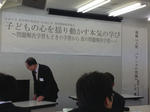
●講演
上田薫先生「人間 バランスの問題」
1月12〜13日@三浦マホロバホテル
案内についてはこちらをご覧ください。
http://www.s-syoshi.com/deta/25nennkanntouannai.pdf
教育実践対話の会は初志の会の関東のいちサークルという位置づけもあります。
教育実践対話の会の松本さんが分科会Dの提案者でした。
各分科会で提案についての検討が行われ、各提案者から振り返りがされました。
分科会A
子どもをどうとらえるのか
自分自身の子どもの見方が固定化していなかっただろうか
その時、教師はどのように出ればよいのか
ということを改めて考えました。
分科会B
教材、子どもの見方、授業の展開のしかたを考えました。
特に、気になる子の姿の意味とその捉え方
参加者の方から「物わかりのいい教師はだめ」という意見を頂いた。
考えさせたいところで「かべ」になれる教師に
ということを考えました。
分科会C
抽出児の一面しか見ることができていなかった。
「私のやりたいこと」が先行して子どもの社会科になっていなかった。
子どもをしっかりととらえて実践をしていきたいと思った。
分科会D
二つのこと
子どもが事実と思いをつないで考えているのか、どのようなことを考えさせていきたいのか
子どもが使った言葉は教師の言葉か、自分の使う言葉を捉え直していきたい
●講演
上田薫先生「人間 バランスの問題」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
研究会後に研究仲間と振り返りをしました。
そのなかで「この研究会は修業の場だよね」と言う言葉が印象的でした。
「how to」「know how」「know what」
を手に入れるのではなく、教師としての地力を付けるために参加したのだなと思いました。
協議会で話し合ったこと一つ一つが力になったと思います。
中野
PR

